野球というスポーツ(あるいは遊び)は、子ども文化の現代史を考える上で、特別に重要な意味を持っていると思う。いまでこそサッカーに話題や人気が移ったが、戦後すぐから長く野球は男の子の外遊びの中心にあった。遊びとしての草野球がまず普及するが、ラジオ、テレビを通してプロ野球の世界が紹介され、次々ヒーローの登場と活躍が伝えられると、後楽園や甲子園が少年の夢の目標にもなった。
ちばあきおの「キャプテン」の第1回が「がんばらなくっちゃ」というタイトルの読み切りとして『別冊少年ジャンプ』に登場したのは、「巨人の星」が完結してちょうど一年後のことであった。
月日は流れ、墨谷二中野球部をすばらしく強力なチームにし、事実上全国大会の決勝戦だといわれる対青葉戦を、死闘のすえに打ち破った谷口タカオは、卒業を迎える。彼は墨谷高校に進学して、もちろん野球をつづけることになるのだが、この段階でちばあきおは、タカオと共に読者を高校野球の場に導いていかない。タカオのあとを丸井が、そしてイガラシがキャプテンを継いで、墨谷二中野球部の物語がつづいていく。そして、墨高のタカオの物語は、1973年から『週刊少年ジャンプ』誌上で「プレイボール」として、新たに展開されることになった。
草野球の彼方に、中学や高校の野球部経由プロ野球行きという夢のコースが浮かび上がってくる。これは鬼ごっこやドッジボールにはない魅力だった。草野球は、ごっこではない。
漫画はいつの時代でも、子どもたちの夢の器だというのがぼくの持論である。子どもたちの夢の見方が漫画に反映し、漫画に夢の見方を学ぶ子どももでる、といった相互関係で、漫画と子どもはつながっているのだ。したがって1948年『漫画少年』の創刊と共に連載が始まった井上一雄の「バット君」以来、野球漫画の傑作は多い。
戦後30年の時点で「戦後の遊びの変遷」をまとめた藤本浩之輔は、次のように十年毎に三期に分けてその特徴を整理している。
現在これに続けて第四期、第五期を十年刻みでくくるとすれば、「興隆」「下降」「沈滞」に続く第四期は、さしずめ「いっそうの停滞期」ということになるかもしれない。つづく第五期はテレビ・ゲームによる「再生期」ということになるが、とりようによっては「頽廃期」ということになるだろか。ただ50年というパースペクティブになると、子どもの遊びをどう考えるかという基軸になる視点そのものが、多少ブレざるを得ない。
第一期
昭和20年〜30年頃。遊びの興隆時代。
スポーツと辻遊びの盛んな時期である。
めやすを終戦(S20)から経済の戦前水準への復活時期(S27〜S28)、または、テレビ放送開始期(S28)においてもよい。
テレビ文化なしの時代。
第二期
昭和30年頃〜40年頃。遊びの下降時代。
テレビ文化と商業主義に次第にからめとられていく時期である。
めやすを神武景気(S30)から新幹線開通・東京オリンピック(S39)においてもよい。
テレビ文化普及進行(1%〜90%)の時代。
第三期
昭和40年頃〜50年頃。遊びの沈滞時代。
テレビ・マンガ・塾・おけいこごと、そして商業主義にからめとられて遊びが閉塞していった時期である。
めやすを新幹線開通・東京オリンピック(S39)からオイルショック(S48)においてもよい。
テレビ文化確立。カラー放送普及進行の時代。
いまは、第三期までの藤本の区分に即して野球漫画の流れを簡単にふりかえっておけば十分である。藤本は第一期について、こうも書いている。
この期の遊びの象徴は、なんといっても「野球」であろう。おとなや中学生は倉庫や物置から昔のくたびれたグローブをさがし出してきた。
しかし、子どもたちにはまわってこなかったので、帯しんや帆布を切って、ボロ屑をつめて、みようみまねでグローブやミットをつくった。
ボールも糸をまいて作ったし、バットも削った。大学野球や職業野球が復活して、ラジオの実況放送がはじまったのも刺激になった。
赤バットの川上、青バットの大下は、子どもたちのあこがれの的であった。したがって、小学校や中学校では校内野球大会とか学校対抗の野球大会などよく行われ、「六三制、野球ばかりが強くなり」と皮肉られたのも、この頃である。
この時期を代表するのが前記の「バット君」である、ちゃんとした道具とそれなりのユニフォームで野球を心ゆくまで楽しむことが、第一期の子どもの夢であった。主人公のバット君は、名投手でも強打者でもない。中学野球部の補欠選手にすぎない。それでも、野球さえできれば、生活上のさまざまな不満も食料不足さえ忘れられた。バット君の最大の喜びは、後楽園にプロ野球を観に行った折、川上哲治選手のホームラン数を当てる懸賞に当って、川上選手から赤バットをもらったことなのである。
野球漫画の変遷は、時代時代の少年の野球に対する期待と夢の推移に規定される。
第二期になると、草野球からプロ野球への夢の階段をかけのぼる少年が主人公になる。
作風において好対照をなす寺田ヒロオの「スポーツマン金太郎」(1959年から『少年サンデー』連載)と、
ちばてつやの「ちかいの魔球」(61年から『少年マガジン』連載)がその代表だろう。
前者は、オトギ村の足柄山ジャイアンツを率いる金太郎と鬼が島ホークスを率いる桃太郎(共に投手で四番打者である)が、決勝戦を延長27回までたたかうが決着がつかず、子どものままプロ野球に唐突に入団し、さらにライバルとして火花を散らすという、いかにも漫画らしい漫画である。
バッターボックスで自ら長嶋を名乗り、金田になったつもりのピッチャーがまっこう勝負に出る、という草野球の基本パターンを、そのまま漫画にすれば「つもり」の実現こそが描くべきテーマになる。
さらに二年すぎると、夢は夢なりのリアリティが欲しくなる。最高のレベルであるプロ野球の世界で活躍するのは、それほど簡単なことではない。
それなりの努力と才能がなければ、プロに上りつめる奇蹟の道はたどれない。
甲子園に行けず屈辱の涙をのんだ二人の高校生が、巨人軍にスカウトされバッテリーを組み、ついには最優秀選手に選ばれるというのが「ちかいの魔球」のストーリーであった。
けれども、おとなの世界は手強いし、きびしい。
主人公の二宮光は、三種類の魔球を開発はするが、やがて肩を痛めて故郷に帰っていく。
この傾向をさらにおしすすめて、プロ野球の(しかも「栄光の巨人軍の」)星となって輝くために艱難辛苦の限りをつくす、そのきびしい道のりを描いたのが、川崎のぼる・梶原一騎の「巨人の星」(66年から『少年マガジン』)であった。
この作品から、藤本の区分の第三期に入る。新幹線、東京オリンピックに象徴される経済の高度成長期で、「根性」だしてがんばれば必ず報われると信じられた時代である。
「巨人の星」は68年からテレビ・アニメ化してヒットする。
以後、「タイガーマスク」(プロレス)、「アタックNo1」(バレーボール)、「あしたのジョー」(ボクシング)などのアニメや、「柔道一直線」(柔道)、「サインはV」(バレーボール)といった実写ものなど、テレビでは雑誌漫画を原作としたいわゆるスポーツ根性路線が人気を集める。
スポーツ根性路線ということばは、テレビの「巨人の星」の主題歌の「思いこんだら試練の道を、行くが男の
「巨人の星」では、魔球を駆使して華やかな勝利をおさめるハイライト・シーンより、その魔球をあみ出す生みの苦しみの過程に力点がおかれ、プロ野球の世界は、単なる舞台設定にすぎなくなる。言いかえれば、人生一般に普遍化できる「生き方」の見本として、栄光をめざして試練に耐えぬく根性を、野球の世界を借りて描くというのが、「巨人の星」のドラマツルギーだったのだ。
これで、スポーツ漫画は行き着くべきところに行き着いてしまったのだ、とぼくは「巨人の星」や「あしたのジョー」の連載が終った『少年マガジン』を眺めながら思っていたのだった。ところが、それがそうではなかったのである。『少年ジャンプ』から、脱スポ根ともいうべき、不思議な野球漫画が現れるのだ。「『少年ジャンプ』の時代」の前史に少し深入りしすぎたかも知れないが、以上のような一応の流れをおさえておかないと、ちばあきおの野球漫画の革命的な意義を説明しにくいのである。
2 キャプテンの衝撃
ある日、東京下町の墨谷二中の野球部二年生の新人谷口タカオが入部した。彼は、野球の名門、青葉学院(私立)からこの学校に転校して来たのだ。レベルが高い青葉学院では、タカオは二軍の補欠にすぎなかったが、墨谷二中の野球部は、青葉から来たと聞いただけで色めきたつ。つい自分の実力を告白しそびれてしまったタカオはやむを得ず野球のことなどなにも知らない大工の父親相手に猛練習を開始する。その甲斐あって次第に実力をつけていき三年進級をひかえた新オーダー発表のとき、サードで四番というレギュラー・ポジションを与えられたばかりか、キャプテンに任命されたのであった。
この導入部だけでも、この作品の発想と設定が「巨人の星」の逆をいくものであることは明らかだろう。「巨人の星」が名門・巨人軍に向かって求心的に上りつめるのに対し、「キャプテン」の物語は、名門からはみ出るところからはじまるのだ。
「なんてこったい……せっかくこんどの学校ではのびのび野球を楽しめると思ってたのに……どうすりゃいいんだ。」
青葉の名選手が転校して来たと誤解され、その誤解を必死でとこうとして果せず、がっくり帰る道々、空き缶が浮かぶドブ川を見下しながら、谷口タカオはこう呟く。ストイックな、そしていくらかファナティックでもあったスポ根の余韻からまだ自由でなかった読者に、このセリフは一服の清涼感と共に野球マンガの原点がいまなお健在であることを思い出させてくれた。ぼくは、このページから受けたはげしいショックをいまでもよく覚えている。のびのび野球を楽しむために名門に背を向ける、そういう野球漫画もあったのだ、と改めて思った。
タカオは突然任命されたキャプテンを懸命に辞退する。誤解が原因の過重な期待に応えるために、精一杯努力した結果選ばれたキャプテンではあったが、「やったあ!」というふうには喜べない。ちばあきおの漫画では、栄光は、それをめざして必死の努力を傾ける目標ではなく、努力の結果、むこうの方からやってくるものなのだ。「タイトル」にもなったキャプテンは、責任重い栄誉ある座には違いないが、タカオはそれをめざしていたのではない。これも「巨人の星」の逆である。
 いくら辞退しても、チームメイトに口々に「お願いします」と迫られれば辞退できるものではない。タカオは嬉しさとテレで思わず帽子を口にくわえ、汗をまき散らしながら、こう呟く。「とうちゃん、お、おれまた、がんばらなっくちゃ!」その表情が実にいい。過去の努力の苦しさを思い出し、キャプテンの栄誉を深くかみしめて感動するのではない。タカオがかみしめているのは、汗くさい帽子である。
いくら辞退しても、チームメイトに口々に「お願いします」と迫られれば辞退できるものではない。タカオは嬉しさとテレで思わず帽子を口にくわえ、汗をまき散らしながら、こう呟く。「とうちゃん、お、おれまた、がんばらなっくちゃ!」その表情が実にいい。過去の努力の苦しさを思い出し、キャプテンの栄誉を深くかみしめて感動するのではない。タカオがかみしめているのは、汗くさい帽子である。
ちばあきおは、涙を描かない。彼が描いたのは飛び散る冷や汗だけだった。
「キャプテン」を読みだすと、いったいなぜそれまでの野球漫画は「血と汗と涙」にああも熱中できたのであろうか、と不思議に思えてくる。
漫画はもともとリアリティよりおもしろさを重視するメディアであって、奇想天外、荒唐無稽な設定やストーリーを得意とする。
さまざまな魔球とそれをあみ出す特訓法、その魔球を打ち崩す秘術といった方向に耽溺していったのには、それなりの理由もあるだろう。
けれども、その空想世界は、読者である子どもたちの現実から、あまりにもかけ離れてしまった、といえないだろうか。
ちばあきおの描く野球選手は、読者と等身大であり、読者の見果てぬ夢を奇蹟的に実現する超能力者ではない。
読者のように、やりたいことをやりたいようにやって、そのことで自己解放というか自己実現に近づこうとしている、ふつうの少年なのである。
彼らにとっては野球は求道の場でも人生のメタファでもなく、現実的な中学校生活の「部活」であり、広い意味での遊びの世界である。
井上一雄の「バット君」のところに。野球漫画は25年ぶりに帰ったのだ、といえるかも知れない。
したがって、墨谷二中野球部は、名門であってはならない。のびのび野球を楽しむ場でなくてはならない。
監督もコーチも顧問も、子どもをシゴき、管理するおとなは一人もいないほうがいい。
タカオを中心とした猛練習の甲斐あって地区予選の決勝に進出したとき、ようやく学校中の注目を集めるようになり、校長先生はじめ何人かの先生が練習をようやく見にくる程度がちょうどよいのである。
それに引きかえ、地区予選で対決し、その後宿命のライバルになる名門青葉学院野球部には、選手をあごで使うサングラスをかけたいやみな監督が配置される。タカオが選んだ「のびのび野球」とは、子どもたちだけの野球だったのだ。星飛雄馬の父一徹が、自らの挫折した夢を息子に託して鬼コーチ役に徹するのに対し、谷口タカオの父は、しょげている息子をはげまそうと、練習相手になってくれるが、野球のことはからきしわからない。この対比も、ちばあきおが作品世界に「おとなの倫理」が入りこむのを極力避けようとしたことを示しているだろう。
3 野球漫画の新しい方向
こういう分家方式とでもいうべきドラマ展開は、スポ根時代にはあり得ないことだった。栄光への道はつねに一直線だったからだ。連載の分岐という事態にあって、ぼくたちは改めてちばあきおの主人公観、登場人物観を学ぶことになる。作者は、タカオをほかの墨谷二中のメンバーとは違う特別な存在としては考えてはいないのだ。名門からはみ出してきた少年を、なぜ特別扱いしなければならないのか。それはタカオがいちばん嫌がっていたことではないか。
もし特別視してしまえば、墨谷二中野球部は、ヒーローにとっての栄光への道の入口あたりのちょっとした道草にすぎなくなるだろう。けれども、よく考えてみれば、少年の日々は、たとえ道草に見えようとも、いつだってだれだって、そのときそのとき精一杯自分というものの最先端を生きているのだ。登場人物一人ひとりに行きわたるちばあきおのやさしい目差しは、スポ根ぼけのぼくや子どもたちを正気に返してくれたのであった。
さっき、中学時代のタカオの最後の試合、青葉とのたたかいを、ぼくは「死闘」と書いた。書きながら、これは注釈が必要だと思っていたのだが、ちば漫画にも技術とエネルギーを使い果し、傷つき倒れる、という場面はめずらしくない。野球をたのしむというのは、手ぬきやなれあいで野球を「弄(もてあそ)ぶ」ことではない。遊びは真剣でなければおもしろくないのだ。しかし、描き方のディテール(項目)が、やはりスポ根とは一味違うのである。


試合中にこんな場面がある。先発のイガラシは一年生のことだし、スタミナが心配だったので、タカオは一人黙々とピッチングの練習を積んでいたが、サードを守っているときファール・フライを深追いし、ベンチに転げ落ち、指の爪をはがしてしまう。控えの選手などいるはずもなく、そのままサードを守りつづけるが、ついにイガラシが疲労困憊、リリーフに立たねばならなくなった。キャッチャーは血染めのボールを黙ってズボンで拭う。ほかに青葉相手に投げられるものはいないのだ。辛うじてダブル・プレーでピンチを切りぬけてベンチに帰ってくるタカオに、「だいじょうぶですか」とイガラシがかけ寄って、思わずタカオの右手にさわると、タカオは「うお……」と叫び、ベンチにうずくまってしまった。
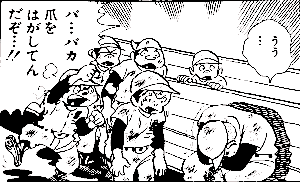
次の三コマ、目をつり上げたイガラシを中心にナインの驚きと緊張の顔がならぶ。「ど、どうしたんだよ」という丸井の疑問に三コマ目でイガラシが答える。「ゆ、指が、おれている……」
チームメイトは救急箱と副え木を探しに走る。応急処置を終えてイガラシが言う。「な、なにもこんなにまでして……」
しかし、ちばあきおは闘志で痛みに耐える谷口の顔をアップにはしない。根性への詠嘆はここにはない。茫然とするナインと、最後の攻撃に奮起を促すキャプテンの指示が一ページ五コマつづき、試合再開である。スコアは9対6。このビハインドを、タカオのバットを折りながらのセンター前ヒットとイガラシの好走塁ではねかえし、墨谷二中は勝利をおさめる。指の骨折をおして投げかつ打つタカオに、悲壮感はなかった。少年たちの熱中の前では骨折さえもが相対化されてしまう。彼らの諦めを知らないファイトは、未来の栄光のために試練に耐える根性ではないのだ。墨谷二中ナインには「いま」しかない。
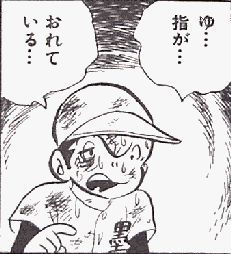 「いま」を未来の犠牲としないこと、あと先のことなど考えず「いま」に集中すること、スポーツの楽しさは、まさにここにあったはずなのに、栄光へのコースが設定されてしまったために、「いま」はみんな階段状の試練というプロセスに組みこまれてしまった。このスポ根の限界を、ちばあきおは破ったのである。
「いま」を未来の犠牲としないこと、あと先のことなど考えず「いま」に集中すること、スポーツの楽しさは、まさにここにあったはずなのに、栄光へのコースが設定されてしまったために、「いま」はみんな階段状の試練というプロセスに組みこまれてしまった。このスポ根の限界を、ちばあきおは破ったのである。
丸井キャプテン、イガラシキャプテンとつづいていく墨谷二中野球部は、それぞれの「いま」を熱くさわやかに生きていく。特別の天才ヒーローはでてこないが、個性的な選手が生まれ、育っていく。のびのび野球をたのしむ伝統は、ハード・トレーニングと共に代々伝えられていくのだ。
一方墨高に進学した谷口タカオは、例の指の骨折以来、人差指が伸びずボールが投げられなくなっていた。それで一度はサッカー部に入ったものの、野球をあきらめられず、結局はまた野球部を続けることになるのだが、この墨高の野球部は地区予選の一回戦で毎年敗退している弱いチームだった。
今年の一回戦に代打用員として出してもらえることになったが、タカオはナインから勝とうという気が全く感じられないのが、不思議でもあり不安でもあった。試合相手のエースが右投げか左投げかも知らず、むろん攻略法など考えてもみない、ただの野球好きの集まりだったのだ。
それでもタカオの偵察ノートとアドバイスのおかげで、バッティングのマトをしぼったり、投手が相手打者の苦手なコーナーをついたりして、善戦する。だが、試合中に人のいいキャプテンは、こう呟く。
「たしかに谷口のアドバイスは適切だ。じっさい効果もでているんだが……。なんかうちのチームにはしっくりこねえんだな。ようするにおれたちゃ、勝ち負けより野球をしてさえいりゃあ満足するんだが、やつには、それだけじゃものたりんらしい。」
「それだけじゃものたりん」のは読者だって同じことだ。けれども、「勝ち負けより野球をしてさえいりゃ満足する」気持ちを忘れてしまってはならない。草野球として出発をとげた戦後日本の野球の原点はここにある。「のびのび野球をたのしむ」ことを身上にしていたはずの谷口タカオは、むろん、そのことを知っている。にもかかわらず、「それだけじゃものたりん」のである。
こうして「たのしむ」とはどういうことなのか、そこを掘り下げていくことが、この新しい野球漫画のテーマになる。「キャプテン」時代からのタカオの不屈の闘志が墨高野球部を徐々に変えていくのだが、それはむろん「たのしみ」から求道へあともどりすることではない。ひたすら技術をみがき、個々のプレーを勝利に結びつけていく努力を積み重ねていくのである。ヒットを打つことも、好走塁もファインプレーも、それが勝利をもたらすからこそ、美しいのだし、たのしいのだ。
そのことをタカオは「自分のやり方」として徹底していく。代打でヒットを打ったことから守備にもつくようになったタカオだが、指の故障のため、ノー・バウンドの送球は不可能である。サードをなるべく浅く守り、早いタイミングでボールに飛びつき、一塁へワン・バウンドで送球する。学校のグランドで、夜の神社で、タカオの特訓はつづく。
地区予選の三回戦で当たることになったのは、シード校の東都実業である。試合の数日前キャプテンはタカオに、こう話しかける。
「おれは、おまえのいっしょうけんめいやろうとする姿は、とてもりっぱだとおもってるよ。しかし、東実に勝とうだなんて考えは、すてるんだな」――これは、どう考えてもキャプテンの言うセリフではない。だが、そのつづきはこうだ。
「そりゃ、おれたちだって、おれたちなりの努力をして試合をするつもりさ。でも、おまえは高校野球ってもんをしらんからむりもねえんだろうけど、限度ってもんがあるんだなあ。たとえば東都実業みたいな野球の名門校ともなると、各地から力のあるやつらがぞくぞく集まってくるのよ。しかもその中には、将来野球で
これには一理ある。タカオも「わかりました」と答えざるを得ない。けれども、「勝ち負けよりも野球さえやっていりゃ満足」の少年たちが、「将来野球でメシをくおうなんてやつら」に勝つことはぜったい不可能だろうか。そんなはずはない、なにかあるはずだ。ちばあきおは、なんでも許される漫画の荒唐無稽さにも逃げず、精神主義にこり固まりもせず、墨高の現実から出発して、できる限りのことをやってみる。作者は「のびのび野球をたのしむ」側の少年たちの立場に立ちきろうとしたのだった。
少しでもはやいワン・バウンドの送球技術を身につけようとひたすら練習に打ちこむタカオの相手をするうち、内野手のバウンド処理はめきめき上達する。
しかもノー・バウンド送球に切りかえたタカオは、曲がった指を使わずにボールをはさむようにして投げるうち、フォークボールのこつを掴むことにもなる。
タカオ一人、東実相手に「実力をためす」はずだった試合は、墨高一丸となっての猛反撃に結実していく。その結果は――。
野球をたのしむというのは、野球の中に自分の全てを投入することだ。
投入した結果が納得できればそれでいい。
できなかったら、未来のためにではなく、「いま」の腐蝕をくいとめるために、よりいっそう深く没入していかねばならない。
そのようなわれを忘れる熱中こそが、不可能を可能にする。
エリートでなくても、ヒーローでなくても、だれだって自分の好きなことを本気でたのしもうとすれば、そこに道が拓ける。
スポ根の彼方に、ちばあきおはそういう野球漫画の新しい方向を示したのであった。
漫画は子どもたちの夢の器であり、したがって野球漫画の変遷は、子どもの野球に対する期待や興奮の質的変化と共にあったことはすでに述べた。
とすると、スポ根全盛のあとに、虚をつくようなかたちでちばあきおの野球漫画が花開いたというのは、子どもの夢の構造のどのような変化に対応したものだったろうか。
藤本浩之輔の時代区分の第三期に入ってから、子ども生活や文化全体に対する管理は、学校の内外を問わず次第に強化されてきた。
放課後も塾やおけいこごとで忙しくなり、非行化防止という思惑もあって中学の「部活」は異常なハード・トレーニングにあけくれするようになる。
少年野球チームが、「外で遊ばない」子どもたちに対するおためごかしの対策として各地にできはじめてもきた。
好きな子ども同士で思いっきり野球をして遊ぶ、などということは、少なくとも都市部の少年たちには、不可能になっていたのである。
草野球の試合をやるには、最低でも八〜十人は仲間が必要だが、もう簡単にはそれだけの人数が集まらなくなっていた。
自由にボール遊びができる場所も少なくなった。
草野球が自由にできたときは、そこを出発点としたヒーロー物語が子どもたちの夢と空想をかきたてた。
しかし、ジャイアンツに入団する漫画のヒーローの運命を追っているうちに、気がついたら草野球を遊ぶ余裕もなくなってしまったのである。
ああ、思い切り野球がやりたい!少年の夢は急速に手元にもどってきたのである。
ちばあきおが掴んだのは、そういう子どもの心だったのだ。
草野球や部活の野球さえが、心からたのしめる形では、もう漫画の中にしかなくなってしまった。
ちばあきおの少年漫画には、少年のさびしさが影を落としている。
しかし、ちばあきお急逝のあと、彼が示した新しい方向は『少年ジャンプ』誌上で十分展開したとは言いがたい。
むしろ、「プレイボール」自体がスポ根の夢よもう一度と荒唐無稽の限りを尽すプロ野球漫画、井上コオ・梶原一騎の「侍ジャイアンツ」(1971年から)と遠崎史朗・中島徳博の「アストロ球団」にはさみうちされるようにして連載されたのであった。
ちばあきおの発想と志をついだのは、キャリアも実力も貼るかに上の水島新司だった、というべきだろう。
『少年ジャンプ』を追うようにして1969年少年画報社から創刊された『少年チャンピオン』に1972年から長期連載されて人気を博した『ドカベン』は、高校野球の原点に立ちもどろうとした野球漫画の傑作であるが、主人公を平凡この上もなく「山田太郎」と名付けるあたり、明らかにちばあきおを意識していた、と思う。
『少年ジャンプ』でちばあきおを受けついだのは、種目こそちがえ高橋陽一の「キャプテン翼」というサッカー漫画だといえるかも知れない。
『少年ジャンプ』は、野球以外のスポーツにも目配りがよく、テニス、ボクシング、ゴルフなどの漫画を連載しつづけ、やがてバスケットボール漫画「スラムダンク」(井上雄彦)を大ヒットさせる。
これらについては、また章を改めて取り上げるが、もう一つ、スポ根とちばあきおとはまた別のひっくり返し方をしたギャグ漫画「ど根性ガエル」の存在も忘れてはならない。
「ど根性」という手垢にまみれかけたことばを、子どもたちの日常生活にもう一度投げ返し、そこに漫画ならではのユニークなキャラクターを生み出したのも、『少年ジャンプ』誌上だったのである。