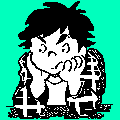 あれから10余年……
あれから10余年……
1994年秋から、没後10年を契機に『ちばあきお名作集』(ホーム社刊)が次々と出されている。遺作となったボクシング・マンガ『チャンプ』や、動物や草花と話ができる自閉症の少年を描いた『ふしぎトーボくん』など、大ヒットした『キャプテン』『プレイボール』以外の、これまであまり目にすることのできなかった作品群である。
ちばあきおが死んだとき、大学生だった僕もやはり強烈に「意外」という想いにとらわれた。誤報だろう、とすら思った。ただそれは、僕が彼の作品を愛読していたからとか、あんな健全なマンガを描く人がなぜ、などという想いとは、少し違っていたようだ。どうもうまく言えないのだが、その時僕は「例えそれが事実であっても、どうしても彼の死を認められない」という心理に陥っていたと思う。彼の死は、いつまでも、そして今も、僕の心の中にうまくおさまってくれない……。
ちばあきお(本名・千葉亜喜生)は1943年1月29日、満州の奉天(現在の中国・遼寧省瀋陽)に生まれた。二Kgそこそこの未熟児で、しかも仮死状態だった。医師が逆さにして尻をたたき、初めて「ヒー……」というかぼそい産声を上げたという。
『屋根うらの絵本かき』は、あきおが生まれた二年後、日本が戦争に負けたところから始まる。暴動を恐れた一家は、深夜ひそかに社宅を抜け出すが、すぐに日本に渡ることはできず、知り合いの中国人の家にかくまわれる。子供たちは、一歩も外出できず、狭い屋根うら部屋で一年以上を過ごした。まるで『アンネの日記』のような、とりわけ体を動かしたい男の子たちには過酷な極限状況である。そんな中で、長男のてつやは、ふとしたきっかけから弟たちに絵物語を描いてやることになる。弟たちは、てつやが不思議がるほどこの絵物語に熱中し、ぼろぼろにすり切れるまで繰り返しこの絵物語を読む。
谷口忠男(ホーム社)は現在『ちばあきお名作集』の編集を担当している。70年からちばの担当になり、この『がんばらなくっちゃ』に登場する「『ジャンプ』編集者」というのも谷口のことである。彼の名前を見て気づく人もいると思うが『キャプテン』の初代キャプテン・谷口タカオの名前は、彼の名前を一字変えてつけたものだ。
だが、ちばあきおはあくまでちばあきおだった。
ちばあきおの臨終の場は、兄・てつやの自宅兼仕事場の二階だった。すぐに救急車で近くの丸茂病院に運ばれたが、すでに遅かった。丸茂病院の水上公宏医師は「ご家族の話では、一ヵ月前に神経科の医者に診てもらったそうですが、典型的なウツ病」のもたらした死だと述べている(『週刊アサヒ芸能』84年10月四号)。
「予感はありましたよ。亡くなったという知らせを聞いた時、『あっついに来たな』と思いましたから」
『あしたのジョー』の、あの有名すぎるほど有名なラスト・シーンは、原作の梶原一騎(クレジットは″高橋朝雄″名儀)が考えたものではなく、ちばてつやのアイデアによるものなのだそうだ。もしちばあきおが燃え尽きたとするなら、決してぷすぷすと不完全燃焼したのではなく、真っ白な灰になって燃え尽きたのだと思いたい。
ちばあきおは、84年9月13日、41歳という若さで死んだ。
ちばあきおがどんな死に方をしたか、というのは、ちばあきおに興味のある人や彼のファンなら誰でも知っているはずだから、僕はここに書くつもりはない。
ちばあきおの死を知った時、多くの人がとらわれたのは「意外」という想いだったと思う。おおよそああした死に方とは縁遠い、健全な世界を描き続けてきたちばが、なぜあの若さで逝ってしまったのか? この想いは、漫画を読む多くの人々の胸の奥に、謎という形でおりたたまれているはずだ。『キャプテン』というマンガが一貫して描き続けてきたのは、どんな逆境であろうと「決して希望を捨てない」少年たちの姿だったのだから。
生い立ち&ちばファミリー
「あきおが大きくなってから『だからおまえは華奢で繊細なんだな』と兄弟でからかったものです」
ちばてつやはそう回想する。
「しかし、どう考えてみるに、彼は四人兄弟のうちでいちばん精密に作られていたらしい」
男ばかりの四人兄弟の三男で、長男はやはりマンガ家のちばてつや(徹弥)、次男の研作は「ちばてつやプロダクション」のマネージャー、四男・樹之は「七三太朗」のペンネームでマンガ原作者をしている。日本のマンガ一家によくある家族経営の小企業だが、その中でも、兄・てつやを中心としたファミリーの結束の強さは、業界でも有名だったという。ちば家では「家族に見せられないようなマンガは描くな」という鉄則があったと、多くのアシスタントたちが証言している。
父・千葉正弥は真面目な性格で、厳格なクリスチャン、印刷会社に勤めていた。母・静子もやはりクリスチャンだが、明るく屈託のない性格で、千葉家を賑やかにしていた。「今でも遊びに行くと『ちゃんとご飯食べた?』って声をかけてくれるんです。もう七十歳を過ぎているのにすごく明るくて元気な人で、この前も詩吟をやってました」(元アシスタント)。古き良き東京下町の情の厚いおばさんといった風情だそうである。
千葉家とちばあきおがたどった歴史を、凝縮して語っている二つの自伝的な短編マンガがある。一つは、ちばてつやが描いた『屋根うらの絵本かき』、もう一つは、あきお自身の描いた『がんばらなくっちゃ』である。
原体験「屋根裏の絵本かき」
『週間新潮』の″墓碑銘″はこうした経緯を解説しながら「後年、知人が語るちば一家の団結力の強さは、幼少のころからの共通の大きな苦労が基になっているともいう」とまとめている。このてつやの自伝短編マンガ『屋根うらの絵本かき』が、どの程度事実に即したものなのかはわからないが、″墓碑銘″氏が言うように、それがちば一家の団結力を高めたのは事実だろう。
しかしそれ以上にちばてつやが語りたかったこと、それは「絵物語」を描くこと、そしてそれを読むこと、つまりマンガが、ちば家にとってはかけがえのない意味を持っていたのだ、という点ではなかったろうか。マンガは極限状態のちば一家を救う、救済的な力を持っていた。だからこそ自分たち一家は、マンガにこだわりぬき、マンガを描き続けるのだ、と。とりわけ、文学作品と比べられて「たかがマンガ」とその価値がおとしめられていた時代に、『あしたのジョー』や『螢三七子』の作者で、稀代のマンガ表現者であったちばてつやは、どうしてもこのことだけは言っておきたかったのではないだろうか。
「ただ、僕は決してあきおに、漫画家になることをすすめたことは一度もなかった」(ちばてつや、『ちばあきおのすべて』より)
しかし、ちばあきおは、ちば家の原体験にひきずられるように、マンガ表現の道へと足を踏み入れていく。
「がんばらなくっちゃ」宿命のマンガ家への道 ちばあきおの自伝的短編マンガ『がんばらなくっちゃ』は、深夜『少年ジャンプ』の編集者がちばの部屋に訪ねていくシーンから始まっている。編集者はちばの白い原稿を見て、「まっしろい本にするわけにはいかないんですよ」と釘を刺し、それから「来月号で自伝をやってもらうことになったんだけど」と来意を明らかにする。
ちばあきおの自伝的短編マンガ『がんばらなくっちゃ』は、深夜『少年ジャンプ』の編集者がちばの部屋に訪ねていくシーンから始まっている。編集者はちばの白い原稿を見て、「まっしろい本にするわけにはいかないんですよ」と釘を刺し、それから「来月号で自伝をやってもらうことになったんだけど」と来意を明らかにする。
ちばは意外なことを聞かれたように「ハテ……、おれはいつから漫画をかくようになったんだろう……?」と思う。そして、ペラペラと話をする『ジャンプ』編集者を前に、回想にのめり込んでいく。
少年の頃「模型飛行機やラジオの部品だの、こわれた時計の歯車やゼンマイが宝物でした」と言うちばは、エンジニアになるのが夢だった。中学を卒業すると、昼間はオモチャ工場に勤め、夜は工業高校の電気科に通うようになる。しかし、入学してまもなく、無理がたたったのか腎臓病になり、自宅療養生活を送る。病気から回復してぶらぶらしているうちに、持ち前の器用さで当時すでに人気作家だった兄・ちばてつやの仕事を手伝うようになる。
そんなある日、ちばは『なかよし』からあきお自身の作品を求められる。27ページ、三ヵ月先の〆切という約束で気軽に引き受けるが、デリケートな完璧主義者のちばにとって、それは予想以上の難行苦行となる。三ヵ月の約束のその作品を完成させるのに、丸一年かかってしまう。
作品を完成させたちばは、酒を飲みながら「じょうだんじゃねえ、こーんなくるしいもんだとはおもってなかったよ。もうこんりんざい漫画なんてかかねえぞ」と言って眠り込む。しかし、編集者からその作品を賞められ、自作を求められると簡単に引き受けてしまうのである。
僕がこの作品を読んでいつも「おや」と思うシーンが一ヶ所ある。徹夜を続けるが思うように作品のできないちばが、公園のベンチで、
「しかし、なんでおれがこんなことに悩まなくちゃならないんだ。おれはエンジニアになるんだ。漫画家なんかじゃない」
と、我に返る瞬間がある。そうなのだ。彼の生の文脈を見る限り、エンジニアになるのが最も自然なはずなのだ。僕がちばの立場なら、その場で編集者に電話を入れて「やはりできない」と言うか、約束した一作を終えた時点でエンジニアへの道を歩み直しただろう。しかし、作品中のちばは、
「またにげか……」
と言うと、自分の頭を自分でガチンと叩き、仕事場に戻っていく。
結局このちばの自伝的な短編マンガは、回想から現実に戻った彼が、『ジャンプ』の編集者に自伝マンガを頼まれ、机に座って「がんばらなくっちゃ」と呟くシーンで終わっている。
あくまでも、ちばあきお
今回の『ちばあきお名作集』の刊行は、谷口と『週間少年ジャンプ』三代目編集長であった西村繁男の発案によるものである。西村は毎週600万部強を売る『週間少年ジャンプ』の基礎を作り、当時『少年マガジン』『少年サンデー』『少年キング』などとの発行部数競争でしのぎを削った名物編集長で、そうしたプロセスを描いた『さらば わが青春の「少年ジャンプ」』(飛鳥新社刊)という著作を持っている。ちばあきおは、当然のことながら、そうした競争の有力なコマの一つでもあったわけである。
谷口はちばと同じ1943年生まれ、同年齢ということもあるが、それ以上に、デリケートなちばと、柔らかい人柄の谷口はよく話が合い、半ば友人のような関係であったという。
 編集者として最初に付き合ったのは『校舎うらのイレブン』という作品だった。兄・てつやのアシスタントをしながら、という事情もあったが、ちばはこの100ページの読み切りマンガに、なんと一年半もの歳月をかける。次作『半ちゃん』(読み切り・100ページ)は、てつやのアシスタントをやめたため予想より早く仕上がったが、それでも半年かかっている。
編集者として最初に付き合ったのは『校舎うらのイレブン』という作品だった。兄・てつやのアシスタントをしながら、という事情もあったが、ちばはこの100ページの読み切りマンガに、なんと一年半もの歳月をかける。次作『半ちゃん』(読み切り・100ページ)は、てつやのアシスタントをやめたため予想より早く仕上がったが、それでも半年かかっている。
こうした経験から谷口は、ちばが遅筆で、読み切りしか描けない漫画家だと思い込んでいた。今考えると、それはある意味では非常に正しかったのだ。しかし、谷口が付き合った三作目の読み切りで『キャプテン』の冒頭に当たる話が非常に面白かったため、『月刊少年ジャンプ』の編集長から連載を依頼するよう命じられる。谷口は「無理させたくないんだけどさぁ……」と言いながらも、その無理を頼まなければならなかった。
ともあれ『キャプテン』は大ヒット作となった。
その頃『週間少年ジャンプ』は、創刊編集長である長野規が辣腕をふるっていた。当時部下であった西村繁男から「未知の惑星から飛翔してきた異星人」「精神構造、あるいは情緒の中で何かが欠落している」と評された長野は、悪名高き「専属契約制度」の創始者でもあったが、同時に、『週間少年ジャンプ』という雑誌を全くの無から少年週刊誌ナンバーワンの座に押し上げた人物でもある。谷口はその長野から「『キャプテン』の評判がいいから、ああいう作品を週間にも欲しい」といわれた。
「僕はちばさんが遅筆なのを知っているから『ちょっとそれは難しいと思いますよ』と返事をしたんです。しかし長野さんは『それはちがうぞ。読者が待ってるんだから、読者の期待には応えるようにしなくてはダメだよ』と言われるんですね」
谷口は苦笑しながら教えてくれた。
もちろん長野にも事情があった。
71年から72年にかけては、『男一匹ガキ大将』に代わるストーリー・マンガが定着せず、『週間少年ジャンプ』は苦戦を続けていた。70年末には、念願の100万部に達した発行部数は、翌年の11月には65万部まで落ち込んでしまう。長野には雑誌の軸となるストーリー・マンガがどうしても必要だったのだ。
このようにして、73年の初夏から『プレイボール』の連載が始まった。長野の『週間少年ジャンプ』の発行部数が常時100万部を超え、『少年マガジン』を抜いて創刊からの悲願であった少年週刊誌ナンバーワンの座を獲得したのは、その年の夏休み以降のことだった……。
谷口が最も鮮烈な印象を込めて語ってくれたエピソード。
『キャプテン』の初期の頃、練習が終わって、ナインが水飲み場で話をするシーンがある。イガラシや丸井たちが、青葉学院のあまりの強さを知ってあせり、言い争っている時に、グラウンドから″コーン、コーン″という音が聞こえてくる。それは谷口が壁に向かってピッチング練習をしている音なのだ。自分たちがドタバタしている時に、キャプテンは黙々とピッチング練習をしている。それを知ってナインの表情が微妙に変化する。
「谷口が練習しているシーンはそのページには出ていなくて″コーン、コーン″という音と、ナインの表情の変化だけで彼らの内面の変化を表現するわけですが、僕なんかから見たらどうでもいいような一コマを、何回も何回も直すんですよ。彼は〆切のギリギリまでねばるタイプで、こっちは〆切が迫ってくるから落ちついていられない。『そんなのどうでもいいよ。読者にだって違いなんかわからない。とにかく早く上げてよ』ってね。
でも、今思うと、モノを作る上でそういうこだわりはとても大切なんですよね」
だが、その谷口が作品の質についてちばあきおに喰ってかかったこともあった。
「もう『プレイボール』の連載が始まっていましたから、75年の頃のことだと思うんですが、なんていうのか、作品のキメが細かくなくなってきたように思ったんです。流して描いているようにも思えたんですよ。もちろん、真面目な人だったから、そんなことはないんだけれど、忙しくなって時間的にもちょっと無理だったのかもしれない。『モウちゃんは強かった』とも重なっていたし、彼もつらかったんですよね
でもこっちとしては、より情感が欲しかったんです。もっと描き込んで欲しかった」
伊豆の宿で打ち合わせをした時、谷口は酒の勢いもあって「最近話の内容が全然面白くない。キャラクターが稀薄なんだよ」と強い口調で言った。
「僕が何か改まった話をすると、彼は『わかった』というかシュンとしてしまうかのどちらかなんだけど、この時はシュンとしてしまったのかな。『谷口、そういうけど、こんな仕事量の中じゃ』って言ったかもしれないけど、わからないな。忘れてしまった。僕も彼のことを思うあまり、きついことを言ってしまったからね」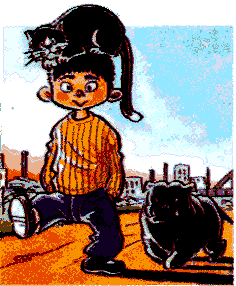 ちばあきおの年譜をたどっていくと、79年三月号で『キャプテン』の連載を終え、82年の四月号から『ふしぎトーボくん』の連載を始めるまで、丸三年間のブランクがある。
ちばあきおの年譜をたどっていくと、79年三月号で『キャプテン』の連載を終え、82年の四月号から『ふしぎトーボくん』の連載を始めるまで、丸三年間のブランクがある。
「もう、仕事からくる疲れで、ちょっとすさまじかったですね。『プレイボール』を始めたときには『これは無理かな』と思ったんですが、本人も一番乗っていた頃だった。その連載が終わって、精神的にも張り詰めた糸が切れた感じになったんです」
それにしても、と僕は思った。ちばあきおほどの人気作家を三年も休ませるとは……。
「そうですね。彼にはずいぶんがんばってもらいましたから。この辺で休んでもいいだろうということになったんですよ」
三年のブランクを経て始まった『ふしぎトーボくん』は、前述したように、文学的で不思議な味わいを持つマンガだったのだが、一般の少年誌でウケるようなテーマではなく、人気投票も五〜六位と低迷する。「また、そろそろ人気が出るものを」ということで、84年四月号から、ボクシング・マンガ『チャンプ』の連載が始まる。そしてその夏に『チャンプ』は人気投票トップに躍り出る。
だが、人気の絶頂の刹那に、ちばあきおはこの世界からかき消えるようにいなくなってしまった。
そして真っ白に燃え尽きて
また『週間新潮』84年9月27日号の″墓碑銘″にマンガ家の吉森みき男は次のようなコメントを寄せている。
「彼は寡作で、一本一本慎重にやる。完璧主義者だったから、雑誌の早いペースに追いつけず悩んでいた。大分前のことですが、不眠症になり、酒をガブ飲みした。ウイスキーやブランデーを平気で一本空ける。いえば、″躁うつ症ノイローゼ″気味のところがあった」
谷口は言う。
「僕も一緒に飲みに行ったこともありました。でも、本当に真面目な人だった。躁うつ病とか言うけど、普通の人だって躁うつの気はあるんです。僕だって同じです。でも、ちばさんの場合は真面目な分、それが本当に深刻だった」
そして、僕も責任を感じてるんです、と小さく言った。
集英社のある編集者は、ちばあきおの死後、酒を飲んだ谷口が「俺が殺したようなもんだ」と荒れている姿を見ている。
ちばてつやのアシスタント時代からの友人であるマンガ家の政岡としやは
「一番親しい編集者で、あきおマンガの花を咲かせたのは何といっても谷口さん。彼とは一緒に仕事をしたことはないけど、集まり合って飲むことはあります。非常に人柄のいい人ですよ。だから余計にショックを受けたと思う」と言う。
71年から79年までちばあきおのアシスタントを勤めた江田二三夫も「谷口さんがそんなに責任を感じることはない」と言う。
「『キャプテン』の後半ぐらいかな。病気(躁うつ病)で描けなくなった時、一回か二回僕が代筆したことがあります」
『キャプテン』の後半といえば、『週刊少年ジャンプ』で『プレイボール』を描いていた時期にも当たる。殺人的な仕事量だったとはいえ、そんなに早くから心を病んでいたとは……。
「病状が悪化して、普通なら下書きと顔のペン入れは必ずあきおさんがやるんですが、その時は本当になかなか描けなくてね。
あきおさんの部屋は僕たちの仕事場の二階にあるんです。最初のうちは三時間に一枚くらいのペースで二階からペンの入った原稿が下りてきた。ところが、段々ペースが落ちてきて、ついにいくら待っても原稿がこなくなってしまった。病気の症状で眠ってしまったんです。その時は担当が谷口さんから別の人に変わっていたんですが、彼が『描いてくれないか』と言うので、メモを見ながら描いたことが一、二回ありました」
一体、何がちばあきおをそこまで追いつめたのだろうか。
「ストレスの発散が途中からできなくなったんですよ。あきおさんに言わせると『糸みたいのがスッと出てきてもつれていくのがわかるんだよね』ってことなんだけど。
調子の悪くなる前は、明日はゴルフがあるって日だと、それまでにきちんと原稿を上げていたんです。『キャプテン』と『プレイボール』をやっていても、それほど大変ではなかった。
ところが後半は『キャプテン』にしても『プレイボール』にしても同じパターンだと飽きられてしまう。パターンに乗って描けば楽なんですよ。しかし、それを壊そう壊そうとしていたから苦労したんです。マンガというのは描けば描くほど考えないとやっていけないわけで、そうすると息抜きの時間が減ってくるんです。せっぱ詰まって、ゴルフもしない、野球もしない。だからストレスがたまっていく。悪循環になるんですよ」
しかし、そうした日常を知っていた江田も、まさかちばがこれほど早く逝ってしまうとは思わなかった。
「朝、寝ていたら友人から電話がかかってきて『テレビでやっているよ』と言うんです。えっ、と思って、それでわかったんです」
政岡としやにとっても、ちばあきおの死は「意外」だった。
「『チャンプ』を見る限り、決してあんなことの影が見えるストーリーではなかったですからね。マンガ家が作品を描くとき、必ず心理的なものが影響してきます。精神的に参っていれば、ストーリー展開に大きく影響するわけです。でも、あの当時の彼の作品にはその影響が読み取れない」
僕自身も、そしてこの取材で僕が出会った人たちにとっても、ちばの死は一様に「意外」だった。だが、そんな中でただ一人だけ、ちばの死を「予感」していた人物がいた。
ちばの死の直前までアシスタントを勤めた高橋広はそう言った。予感……?
「傍から見ていると、このままじゃ死んでしまうなという状況で仕事をしていました。自分のことを追い込むような仕事ぶりなんです。最後の頃は、仕事にいっても真っ白い紙があるだけだった。
こっちにしてみれば、少しでも何か描いてあれば何とかするんです。とにかく描いてしまえばいいじゃないですか、と思うんですけど、本人にすればこだわりがあるからどうしても描けない」
一体、ちばあきおは何にこだわっていたのだろうか。
「前から描きたかった絵があったんです。本質的には、単純に単純にしていこう。その方向をとことん突きつめていこう、ということなんです。
描き込む絵は誰でも描けるじゃないですか。省けるものをどれだけ省いていっても、その絵が生きていさえすればいい、ということだったんでしょうね。描かないで見せられれば一番いいという考え方になっていたんです」
ギリギリの単純化と、その単純さの中にひそむ線の生を、ちばあきおは突きつめようとしていたという。
「だから、本当はバックも一人で描きたかったんだと思いますよ。
アシスタントに入って、マンガというより、とにかくあきおさんが好きでね。何とか気に入られたいというか認められたいというか、あきおさんが喜ぶことをしたかったんですよね、きっと。そういう人に出会えたことは、とても幸せなことですね。
あきおさんがいなくなって、僕自身もあとを継ごうと思って、思い上がっていた時期があったんです(笑)。あきおさんのやろうとしたことを突きつめていこうとしたんですよ。でも途中からダメになりましたね。こりゃダメだと思いました。あきおさんはあきおさんがやるしかないんです」
もし今ちばあきおが生きていたら、どんな作品を描いていたろうか。それを、ちばあきおになろうとした高橋に尋ねると、笑いながら、「案外、宗教の方に行ったかもしれませんよ」と答えてくれた。これは示唆に富む指摘で、実際「消えたマンガ家」の中には、宗教方面に消えた人が数多くいるのだ。
一昨年の春、政岡はちばあきおの夢を見た。夢の中のちばが「マー坊、ぼちぼちこっちへ来いや」と言うので、政岡は「俺はあかん。まだまだ借金もいっぱいあんねん」と答えたという。政岡はその時のちばの明るい表情をみて「いろんな苦しみを振り切って、あっちの世界で楽しくやっているんだな」と思ったという。
「あきおさんのリラックスした時の顔は、童顔だからってこともあるけど、本当に楽しそうな表情になるんですよ」
政岡の話を聞いた江田は、心から嬉しそうに顔をほころばせた。